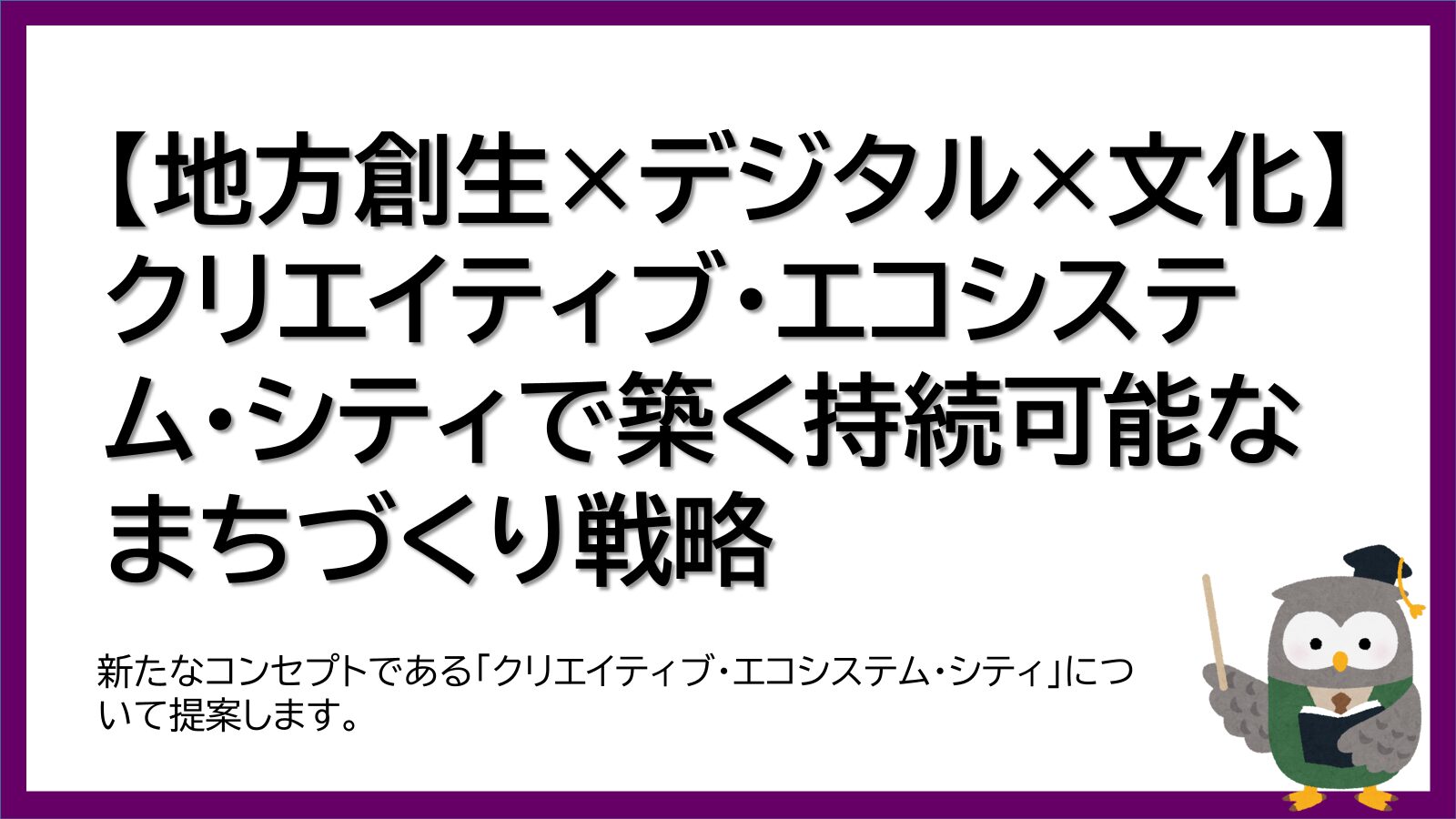人口減少、気候変動、経済衰退…複雑化する都市課題を乗り越える鍵は「創造性」と「共創」にあります。本記事では、文化・テクノロジー・市民参加を融合した次世代都市モデル「クリエイティブ・エコシステム・シティ」の概念、構成要素、地方自治体による実践方法、海外の先進事例までを解説。これからの地方創生に必要なビジョンと実装ステップが分かります。
1. 「クリエイティブ・エコシステム・シティ」とは何か?
現代の都市は、単に「便利で経済的に豊か」なだけでは持続可能とは言えません。人口減少、高齢化、産業空洞化、コミュニティの希薄化、さらには気候変動といった複雑な課題が同時多発的に起きている今、都市づくりの在り方も根本から問い直されています。
このような背景の中で、「クリエイティブ・エコシステム・シティ(Creative Ecosystem City)」という新たな都市モデルを提唱します。
このコンセプトは、文化・芸術・テクノロジー・教育・環境・市民参加など、都市が持つ多様な資源や要素を有機的に結びつけ、それらを持続的に育む「都市の創造的生態系(エコシステム)」を築くことで、地域に新しい価値と活力を生み出そうというものです。
かつての「クリエイティブシティ(創造都市)」が文化や芸術を軸とした都市ブランディング戦略だったのに対し、また「イノベーティブシティ(革新都市)」がテクノロジーやスタートアップ支援に特化していたのに対し、本コンセプトは両者を融合的・横断的に捉え、「都市の未来を包括的にデザインする枠組み」として位置づけられます。
2. なぜ今、「クリエイティブ・エコシステム・シティ」が必要なのか?
① 文化だけでは都市は持続しない
2000年代初頭に注目された「創造都市(Creative City)」のアプローチは、都市の魅力を高め、観光や創造産業の活性化に大きな効果をもたらしました。しかしその一方で、経済的持続性や社会的包摂の課題が指摘されてきました。
例えば、アートフェスティバルやクリエイティブ拠点の整備が一部の関係者に恩恵をもたらす一方で、地域全体に利益が波及しにくい、もしくは住民が取り残されるような事例も生まれてしまったのです。
② 技術だけでは人は集まらない
一方で、テクノロジーを基盤とする「イノベーティブシティ」は、スタートアップ支援やスマートインフラの整備を通じて新しい都市機能を創出してきましたが、その多くが市民の暮らしや地域文化との乖離を招きました。
最新のIoTやAI技術が導入されても、それが市民の価値観や生活スタイルに合っていなければ、真に持続的な都市づくりにはなりません。
③ 複雑な都市課題に対応する「融合型モデル」が必要
現代の都市課題は、もはや単一の手法では解決できません。地方自治体が直面しているのは、少子高齢化、空き家問題、エネルギー転換、若者の流出、気候変動、地域経済の衰退といった複合的かつ構造的な課題です。
こうした課題には、「文化」「技術」「教育」「環境」「市民社会」といった複数の要素を横断的に組み合わせることが不可欠です。そのための新たな視座が、クリエイティブ・エコシステム・シティなのです。
3. 都市の創造性を構成する5つの柱
クリエイティブ・エコシステム・シティは、「創造性」を都市の中核価値とし、次の5つの分野でその創造性を具体化します。
1|文化的創造性
伝統文化、地域芸能、現代アート、食文化、デザインなど、地域に根ざした文化資源を再発見し、それを現代社会に適応させながら新しい価値に転換します。たとえば、職人技術とデジタルファブリケーションを掛け合わせた工芸の革新などが好例です。
2|技術的創造性
デジタル技術(AI、IoT、ブロックチェーンなど)を活用して、地域課題を解決する都市サービスを開発。例として、地域通貨アプリや防災IoT、スマート農業などがあり、これにより「人に優しい技術導入」が可能になります。
3|教育的創造性
子どもから高齢者までが学び続け、創造力や問題解決力を高められる学習環境を整備します。STEAM教育や市民大学、ワークショップ型の生涯学習などを通じ、地域が「学びの場」として機能します。
4|社会的創造性
行政任せではなく、市民やNPO、企業が連携し、地域課題を共に考え、共に解決する共創の仕組みをつくります。デジタル民主主義や市民参加型予算、市民ラボ(リビングラボ)、シビックテックなどの制度整備がカギです。
5|環境的創造性
再生可能エネルギーの導入、循環型経済の実現、自然と共生する都市構造の形成など、都市の環境性能そのものをクリエイティブにデザインしていくことが求められます。脱炭素だけでなく、地域の景観や風土も考慮したまちづくりが重要です。
4. 地方自治体が実践すべき5つの取り組み
地方都市でも、創造性を都市政策に組み込むためには、以下のような具体的な取り組みが鍵となります。
■ 1|地域文化を活かした観光・教育の再構築
地域に眠る歴史資源、伝統文化、ストーリー性を活用し、単なる観光資源ではなく「学びと交流のコンテンツ」に昇華させる。
■ 2|デジタル技術との融合
行政DXや地域交通のスマート化、デジタル住民サービス、スマート農業などを通じて、技術が生活の質を高めるように設計する。
■ 3|創造的人材の育成と定着
若者や移住者のための起業支援やクリエイティブ人材育成講座、市民大学のような学びの場を通じて地域内の人材循環を生む。
■ 4|市民参加と共創の仕組みづくり
市民会議や共創ワークショップ、シビックテックプロジェクトなどを通じて、市民を単なる“対象”ではなく“主体”に位置づける。
■ 5|サステナブルな地域設計
脱炭素住宅、地域エネルギー会社、マイクロモビリティの導入などにより、持続可能でコンパクトなまちを構築する。
5. 実現のための政策プロセス
「クリエイティブ・エコシステム・シティ」を実現するには、段階的かつ実効性のある政策プロセスが不可欠です。以下の5つのステップを通じて、地域に根ざした創造的な都市づくりを推進していくことが求められます。
1)ビジョンの策定と共有
まずは、自治体内部だけでなく、住民・企業・大学・NPOなど地域の多様な主体とともに、対話を重ねて都市の将来像を描きます。全員が共感できる“地域の未来像”を共有することが、取り組みの土台となります。
2)連携体制の構築
「産学官民+市民」の五者による連携プラットフォームを整備し、各セクターが役割と資源を持ち寄って共創する仕組みをつくります。単なる意見交換の場ではなく、具体的なプロジェクトが動き出す実行組織を構築することが重要です。
3)資源の確保
外部からの補助金や企業からの投資、大学との連携、人的ネットワーク、空き施設の活用など、多様なリソースを柔軟に組み合わせて、継続可能な運営体制を築きます。地域内外の知恵と資金の流れを可視化・最適化することが鍵です。
4)モデル事業の実施
小規模でもインパクトのある取り組みから着手し、成功事例として可視化します。PDCAサイクルを回しながら段階的に拡大し、地域に創造的な成功体験を蓄積することが持続的な変化を生み出します。
5)評価と改善
数値的なKPIだけでなく、住民の納得感や幸福度といった定性的な評価指標も含めて、プロジェクトの進捗と影響を多面的に評価します。結果を踏まえて改善を繰り返すことで、地域に根ざした価値創出が持続していきます。
6. 海外の先進事例紹介
バルセロナ 22@地区 (スペイン)
かつての産業地帯であったポブレノウ地区を再開発し、情報通信、デザイン、バイオ、エネルギー、メディアなどの革新的産業を集積した都市再生プロジェクトです。この地区では、大学、研究機関、スタートアップ、クリエイターが集い、文化とテクノロジーが融合するエコシステムが形成されています。公共空間の整備や住民参加型の都市計画も進められ、経済成長と社会包摂を両立するの先進事例です。
マンチェスター(イギリス)
産業革命を支えた工業都市から、音楽、アート、メディアを軸とする創造都市へと転換を遂げた代表例です。特に音楽文化の影響は大きく、都市アイデンティティの再構築に寄与しました。再開発では文化施設とテクノロジー産業を融合させ、市民や大学、スタートアップとの連携による都市の再生が進行。創造性と革新性を共存させた「クリエイティブ・エコシステム・シティ」の先進モデルです。
アムステルダム(オランダ)
文化の多様性と先進的なデジタル政策を融合させた「クリエイティブ・エコシステム・シティ」の好例です。都市内にはアート、デザイン、スタートアップが共存し、市民参加型のスマートシティ政策や循環型経済への転換も進行中。創造産業を支える文化施設やコワーキング空間が点在し、大学・自治体・市民が協働するオープンイノベーション体制が整備されています。文化と技術、環境と経済が融合する持続可能な都市モデルです。
7. まとめ:創造性と共創が地域の未来を切り拓く
「クリエイティブ・エコシステム・シティ」は、経済成長や競争力に偏らない、人間中心・文化主導・共創型の都市づくりを目指すモデルです。地域の個性と創造性を活かすことが、結果として持続可能な成長や新しい価値を生み出します。
地方自治体がこの考え方を導入することで、限られたリソースでも都市の魅力や活力を高め、市民の誇りや参加意識を育むことができます。これこそが、真に地域に根ざした未来志向の地方創生といえるのではないでしょうか。
<参考文献>
野澤一博(2025)「産業都市の再生に関するホリスティック・アプローチ:オランダのアイントホーフェンを事例として」『流通經濟大學論集』第59巻4号