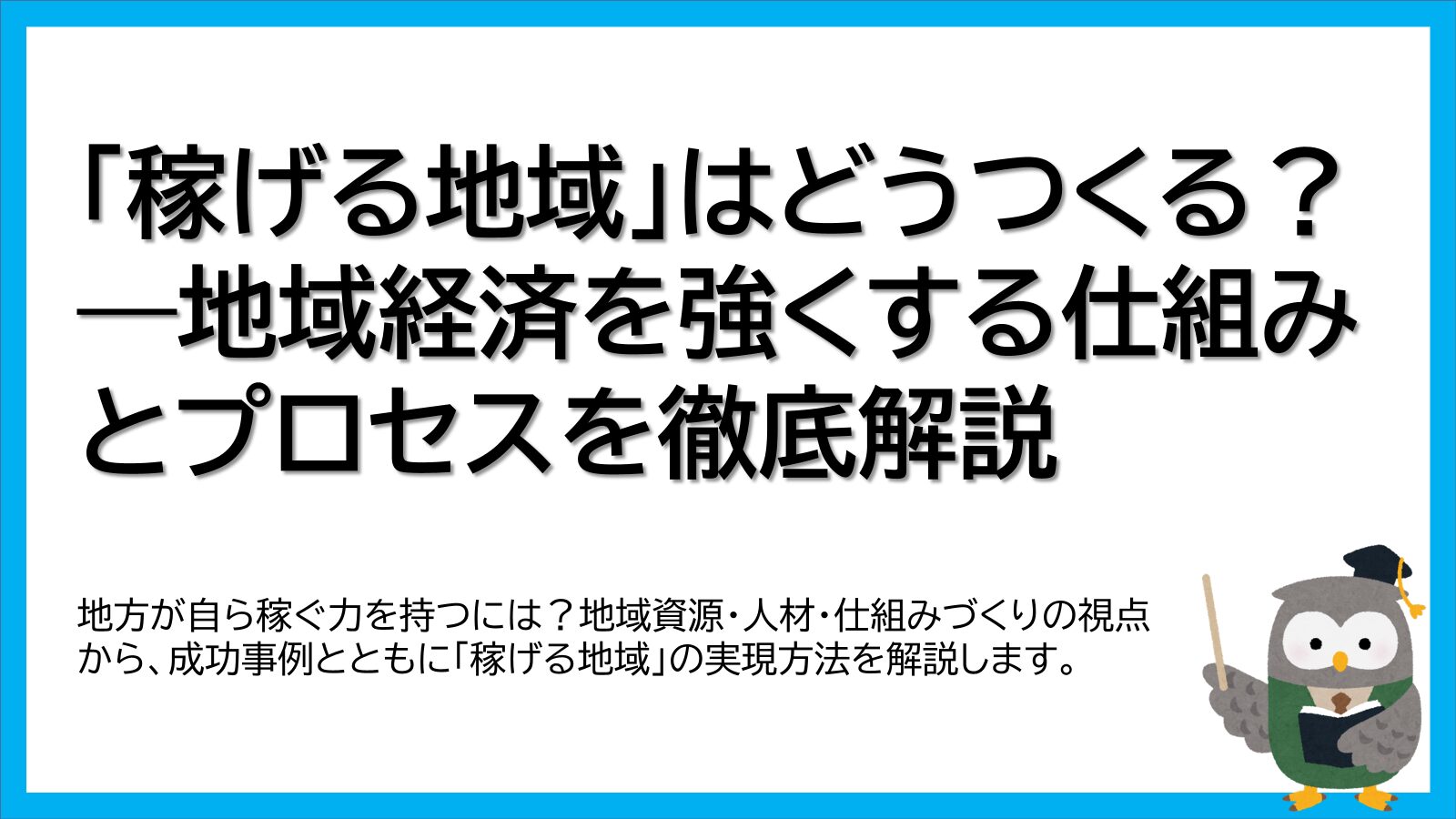人口減少、産業空洞化、若者の流出――多くの地域が直面する厳しい現実。そんな中で「稼げる地域」として注目される自治体が少しずつ増えています。では、どうすれば地域が自ら稼ぐ力を持てるのか? 本記事では、地域の現状を踏まえながら、稼げる地域になるための要素とプロセス、そしてその課題についてわかりやすく解説します。
1.なぜ今「稼げる地域」が必要なのか?
現在、日本各地の地方自治体が直面している最大の課題のひとつが、地域経済の自立化です。国からの支援に依存せず、自らの力で安定した収入と雇用を生み出せる「稼げる地域」への転換が求められています。その背景には、次のような深刻な構造的問題があります。
1) 深刻化する人口減少と高齢化
日本全体で人口が減少する中、地方では若者の流出と高齢化の進行が特に著しく進んでいます。たとえば秋田県では、2022年時点で65歳以上の高齢者が人口の38.6%を占め、全国でも最も高い割合となっています。
現役世代の減少は、地元産業の担い手不足や地域内消費の縮小を引き起こし、地域経済の持続性を揺るがしています。
2) 雇用の質の低下と都市への人口流出
地方における雇用は、第三次産業への偏りや都市部企業の下請け構造に依存しており、不安定な労働環境が問題になっています。
たとえば北関東のある町では、工場閉鎖により安定した雇用が消失し、代わりに派遣労働が主流となったことで、地域住民の可処分所得が大きく減少しました。その結果、若年層はより良い雇用機会を求めて都市部へと流出し、地域の人口減少が加速する悪循環が生まれています。
3) 財政格差と依存体質の固定化
総務省のデータによると、地方交付税への依存度が高い自治体では、自主財源比率が30%未満のケースも珍しくありません。
たとえば高知県のある町では、歳入の約7割が国の交付金に依存しており、自主的な政策や事業展開が非常に難しい状況にあります。このような財政構造では、地域独自の戦略的な投資や長期的な成長ビジョンを描くことが困難になります。
3) 「稼げる地域」こそが持続可能な地域社会のカギ
こうした課題を打開するには、地域が自ら「稼ぐ力」を持つこと=地域経済の自律性を高めることが不可欠です。
たとえば、長野県小布施町では、地元産の栗を活かした観光やスイーツ事業、アートや文化を融合したまちづくりを通じて、来訪者と定住者の増加、そして自主財源の確保に成功しています。
「稼げる地域」が実現すれば、地域で起業したり、地元で働いたりする選択肢が増え、住民の暮らしに希望と多様性が生まれます。外から資本や人材を呼び込み、内から人材を育てるという好循環が、持続可能な地域経済の基盤になるのです。
4) 「補助金頼み」から「稼ぐ仕組み」へ
これからの地方経済は、「補助金で維持する地域」ではなく、「自分たちで稼いで循環する地域」へと転換する必要があります。
そのためには、自治体、住民、企業、大学、NPOといった多様な主体が連携し、共創による稼ぐ仕組み=地域経済のエコシステムを育てていくことが重要です。
2.「稼げる地域」に必要な4つの資源
地域が「稼ぐ力」を身につけるためには、単にお金を稼ぐビジネスモデルを持つだけでは不十分です。地域の特性を活かし、持続的に価値を生み出すためには、次の4つの資源を戦略的に活用することが欠かせません。
1)地域資源の発掘と活用
第一に必要なのは、地域の中にある「宝」を見つけ出し、再編集する視点です。観光資源や特産品、伝統産業など、一見平凡に見えるものでも、価値の「見せ方」次第で外部の人々を惹きつける力になります。
たとえば、島根県の海士町では、離島であるというハンディを逆手に取り、離島ならではの自然や食、教育プログラムを磨き上げ、「学びと関係人口」の観光モデルを確立しました。地元の隠岐牛やサザエ、地酒などの特産品も、ECサイトやふるさと納税で人気となっています。
このように、資源の価値は「あるかどうか」よりも「どう編集するか」が重要なのです。
2)ヒト資源(人材)の確保と育成
次に欠かせないのが、人を育て、呼び込む力です。地元で事業を継ぐ人、起業する人、外から新たにやってくる人――こうした多様な人材が地域の稼ぐ力を支えます。
長野県塩尻市では、IT企業や大学と連携し「スナバ」という人材育成と起業支援の場を設け、学生や地域住民が一緒にビジネスのアイデアを形にしています。さらに市内の中小企業も巻き込んだプログラムにより、地域に根付く新たな担い手が次々と育っています。
このように、教育機関や企業との連携を通じて、「外から人を呼び、内から人を育てる」仕組みが求められます。
3)知識と技術の導入
「稼げる地域」には、地域に知恵と技術を流し込む導線も必要です。とくに、ECサイト、クラウドファンディング、SNSなど、デジタル技術の活用によって販路は無限に広がります。
新潟県燕三条地域では、金属加工業の高い技術を武器にしつつ、海外市場向けのプロモーションやネット販売に力を入れています。クラウドファンディングで新製品の資金調達を行い、海外バイヤー向け展示会とも連携し、「職人のまち」から「世界に売るまち」へと転換を果たしました。
また、産学官連携によって新技術を導入したり、大学の研究シーズを活かして地元企業の技術革新を図ることも、競争力の源泉になります。
4)ネットワークと信用
最後に、地域が継続的に稼ぐには、人と人とのつながり=ネットワークと信用が必要不可欠です。特に地域内での協働体制と、都市圏など外部との接続性の両立が求められます。
香川県三豊市では、地元事業者が共同で観光戦略を立て、「父母ヶ浜」や「UDON HOUSE」などを軸に地域全体のブランドを形成しました。また、都市部の企業や大学との交流も活発で、二拠点居住やリモートワーク環境の整備により、移住者や関係人口が増加。地元の信用と都市の知を組み合わせることで、新たな経済循環を生み出しています。
信頼の積み重ねこそが、挑戦を支え、外部からの投資や協力を呼び込む土台になるのです。
このように、「稼げる地域」を実現するためには、モノ・ヒト・知恵・つながりという4つの資源をいかに戦略的に組み合わせるかがカギを握ります。それは、単なるビジネスモデルの構築ではなく、地域という土壌に根ざした「仕組みづくり」そのものなのです。
3.「稼げる地域」になるための3ステップ
「稼げる地域」をつくるためには、いきなり大規模なプロジェクトに着手するのではなく、地域の特性と資源を見極め、小さな成功を積み上げ、やがてそれを持続可能な仕組みへと育てていく段階的なアプローチが有効です。ここでは、地域が稼ぐ力を獲得していくための3つのステップを紹介します。
Step 1:地域を知り、強みを言語化する
第一歩は、自分たちの地域が持つ強みや魅力を言語化することです。その際に有効なのが、SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)というフレームワークです。内的資源と外的環境を整理することで、地域のどこに可能性があるのかが見えてきます。
たとえば、北海道・十勝地域は「寒冷地」「人口希薄」という弱みを、むしろ「食と農の王国」「大規模農業による付加価値の創出」という強みに転換しました。地元の乳製品や小麦、肉類を活かした加工品をブランド化し、「十勝ブランド」として道外にも販路を広げています。
また、広島県尾道市では、空き家問題を逆手にとり、リノベーションによるまちづくりを展開。古民家カフェやゲストハウスが連携し、「若者が訪れ、暮らし、起業するまち」という新たな地域イメージを定着させています。これらの事例に共通するのは、地域アイデンティティの再発見と発信力の強化です。
Step 2:小さな経済の成功体験を積む
次の段階では、地域の強みを活かしたスモールビジネスを起こし、「稼げる」体験を積み上げることが重要です。最初から大規模な開発に走るのではなく、マーケット志向に基づいた実験的な事業を立ち上げ、改善を重ねていく姿勢が求められます。
たとえば、山梨県北杜市では、地元農家と連携したクラフトビール醸造所が誕生しました。地元のホップを使い、観光客向けのブルワリーツアーやビールフェスも開催。小さな規模ながら、地域内の農業、観光、飲食をつなげる好循環を生んでいます。
また、宮崎県綾町では、地元有機野菜を活用したカフェやマルシェが住民主導で立ち上がり、環境保全と経済活動を両立するモデルとして注目されました。こうした「稼げるモデル事業」が地域の中に点在することで、新たなチャレンジが次々と生まれる土壌が育ちます。
「誰のために稼ぐのか?」という問いに答え、ターゲット顧客のニーズを意識したサービス設計が、地域ビジネスの成功を左右します。
Step 3:エコシステムをつくる
最後のステップは、個別の成功を持続可能な地域全体の成長へとつなげる「エコシステム(生態系)」の構築です。稼ぐ力を持つプレイヤー同士がつながり、資金・人材・情報が地域内で循環する仕組みを育てることが鍵となります。
その好例が、福井県鯖江市です。眼鏡フレームの製造で有名なこの地域では、職人、行政、企業、地元の若者が連携して「地域活性化プランコンテスト」を開催。オープンデータの活用や市民主導のアイデアソンなど、市民の力を結びつける仕掛けを次々と打ち出しています。結果として、新しいビジネスや雇用も生まれています。
このように、自治体はエコシステムの「設計者」「つなぎ役」として、民間・教育・NPOなど多様なプレイヤーを結びつけるハブ的存在になることが求められます。
地域が稼ぐためには、単に産業を誘致するだけでなく、「地域の価値を見つけ」「それを小さな形で試し」「信頼のネットワークを育てる」プロセスが重要です。それは時間のかかる道ですが、一歩ずつ積み上げることで、やがて「稼げる地域」という持続可能な経済基盤が築かれていきます。
4.「稼げる地域」が直面する課題
地域が「稼げる力」を手に入れることは希望につながる一方で、いくつかの重要な課題も抱えています。持続可能で誰もが恩恵を受けられる地域経済を築くためには、以下の点に注意しなければなりません。
1)成功の属人性:キーマン依存の脆弱性
地域づくりにおいてしばしば見られるのが、特定の起業家やリーダーの存在に依存してしまう「属人化」です。たとえば、ある地方都市では、移住者の若手クリエイターが仕掛けたアートイベントが注目を集めましたが、その人物が別地域に移ると同時にプロジェクトが失速。個人の熱意だけでは、地域全体の稼ぐ仕組みは持続しにくいという現実が浮き彫りになりました。制度や組織的な担保がなければ、一過性のブームに終わってしまうのです。
2)成功の再現性:横展開の難しさ
他地域の成功事例を真似すればうまくいくとは限りません。たとえば、古民家リノベーションによるまちづくりで成功した尾道市の事例を模倣した地域が、観光客のニーズや交通アクセスの課題に直面し、成果が出なかったケースもあります。地域には固有の歴史、資源、人材があり、「どこでも同じモデルが通用するわけではない」という現実に向き合う必要があります。成功の背後にあるプロセスやコンテキストを丁寧に読み解くことが、再現性の鍵となります。
3)成長と分配:誰が「稼げる」のか、地域内格差の発生
地域が稼げるようになったとしても、その恩恵が一部の人に偏ってしまうと、新たな地域内格差を生む危険があります。観光業や新産業で得た利益が外部資本や特定事業者に集中し、地元住民の所得や生活環境が改善されないという事態は各地で見られます。たとえば、某観光地では民泊業者が急増し地価が高騰。若い住民が家を借りられなくなるという「成長の陰のひずみ」が起きました。誰が参加し、誰が利益を享受するのかというインクルーシブ(包摂)な視点が不可欠です。
4)観光化・商業化の副作用:住民の暮らしとのバランス
観光や商業が地域の経済を支える一方で、過度な観光化や商業化が住民の暮らしに影響を及ぼす問題も無視できません。たとえば、京都市の中心部では、インバウンド需要により地元の商店街が観光客向けに変貌し、地元住民が日常的に利用できる商店が減少したことが議論を呼びました。こうした事例は、「稼ぐ地域づくり」において、住民の生活の質とのバランスを取ることが重要であることを示しています。
地域が経済的に自立することは重要ですが、それが「誰のための稼ぐ力なのか」を常に問い続ける姿勢が必要です。持続可能性、住民参加、公平な分配を視野に入れた設計こそが、真に意味のある地域経済の成長につながるのです。
5.これからの地域へ:稼ぐ仕組みを「共に」育てる
「地域の稼ぐ力」は、もはや自治体や一部の企業だけで育てられるものではありません。そこには、住民、大学、NPO、起業家、地域外の支援者など、多様な主体の連携と協働が必要です。地域に関わるすべての人が「共につくる」という視点で関与することで、初めて持続可能な経済の循環が生まれます。
今や、トップダウンの開発ではなく、ボトムアップの「地域経営」の時代です。小さな試行錯誤や実験を許容する文化と、それを支える対話の場こそが、稼げる地域の土台となります。稼ぐ仕組みは一夜にしてできるものではありません。挑戦と失敗を繰り返しながら、地域が自ら学び、進化し続けることが、真の自立へとつながるのです。