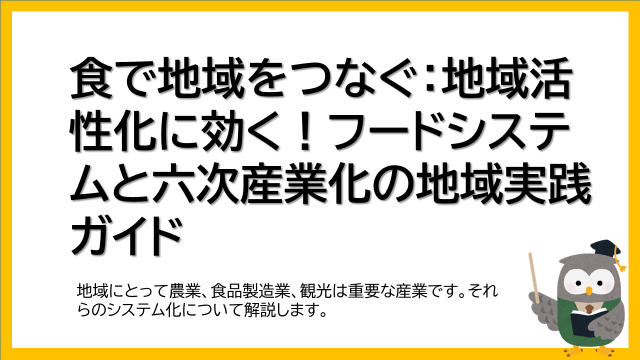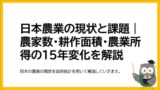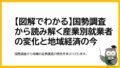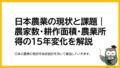食は、栄養や嗜好だけでなく、地域の産業、文化、風土、観光、経済をまるごと巻き込む「地域づくりの軸」になりつつあります。その中心にあるのが「フードシステム」という考え方です。さらに、近年は六次産業化の取り組み、ガストロノミーの価値、観光開発と地域ブランドの強化、そしてそれらをつなぐ食糧産業クラスターの形成が重視されるようになっています。本記事では、これらのキーワードを一つの流れでとらえ、地域実践を支える視座を紹介します。
※日本の農業の現状については、下記の記事をお読みください。
1. フードシステム:食の全体像をとらえる
フードシステムとは何か?
まずは「フードシステム」という言葉を説明しましょう。フードシステムとは、次のような食に関わる一連の流れを指します:
農林水産業 → 食品製造業 → 食品卸売業 → 小売業 → 外食産業 → 消費者の食卓
このように、農場からフォーク(farm to fork)までのすべてのプロセスを一つの「システム」としてとらえるのが特徴です。つまり、農業だけでなく、加工、流通、販売、消費までを含めた総合的な視点で食の経済や社会を考えるということです。
このフードシステムの視点に立つと、地域内での「食の循環」や、「誰と誰がどう連携するか」といった垂直的・水平的なつながりが重要になります。
2. 六次産業化:1×2×3=地域価値の創造
1) 六次産業化とは、
このフードシステムの中で、地域活性化の切り札として期待されているのが六次産業化です。
- 第1次産業(生産):農業・漁業・林業
- 第2次産業(加工):食品加工・製造業
- 第3次産業(販売・サービス):流通・小売・観光
これらを組み合わせて、「1×2×3=6次産業」とする考え方です。
たとえば、農家が自らトマトを育て(第1次)、トマトジュースを作り(第2次)、直売所やECサイトで販売する(第3次)といったように、生産者自らが川中・川下のプロセスに関わることで、付加価値を生み出します。
2) 六次産業化の意味と可能性
六次産業化には、単なる産業の垂直統合にとどまらない多面的な意義があります。
地域経済の自立と循環
それぞれの産業がバラバラに動いていた地域の中で、連携が生まれることにより、地域内での経済循環が生まれます。これは、地域外への利益の流出を防ぎ、地元での雇用や所得の創出にもつながります。
多様な担い手による展開
六次産業化を進める担い手は、必ずしも企業だけではありません。たとえば、
- JAや地域法人による産業政策系の取り組み
- 女性起業家、家族経営、小規模NPOなどによる地域社会政策系の取り組み
といったように、多様な主体が参入可能です。こうした多様性こそが、地域に根ざした柔軟なイノベーションの源泉となります。
【事例】高知県・馬路村 :ゆずの村の物語型六次産業化
人口800人ほどの小さな村が、「ゆず」という地域資源を軸に、一体的なブランド戦略とフードシステム型六次産業化を実現しています。
フードシステム的特徴:
- 川上:高齢者や小規模農家も参画できるゆず栽培システム
- 川中:自社工場でジュース・ぽん酢などの製造(JAが主導)
- 川下:カタログ通販、ふるさと納税、地元物産館などでの直販
- ブランド価値の醸成:「ごっくん馬路村」などネーミング・パッケージ戦略が全国で浸透
- 消費者との関係性:通販顧客との関係を「村の仲間」として構築
六次産業的成果:
- 規模は小さくても高付加価値を生む「顔の見えるフードシステム」
- 雇用創出と地域誇りの再生
- 外部依存からの脱却と自主経営の実現
➤ 小さな自治体がフードシステムの視点で六次産業化を成功させた代表例です。
3) フードシステム的視点から考える六次産業化
六次産業化をフードシステムとしてとらえると、次のような課題と可能性が見えてきます:
- バリューチェーンの構築:生産から加工、販売、そして消費者までをどう一体的につなげるか。
- 技術・資本・参入障壁の問題:加工や販売に進出するには新たな知識や投資が必要。地域内でのサポート体制が鍵に。
- 地域クラスターの形成:異業種との連携や観光との融合によって、新しい産業集積=クラスターが生まれる可能性。
- 食の安全・安心・ストーリー性:消費者にとっては、誰がどこでどう作ったかが「価値」になる時代。地域性や物語性が大きな武器になります。
2. ガストロノミー:知と文化で食の価値を高める
ガストロノミーは、単なる「美食」ではなく、食材の背景、調理技法、風土、文化、倫理、環境配慮などを含む総合的な食文化の概念です。
食材を「地域の物語」として提示し、観光・教育・地域誇りと結びつけるツールとして注目されています。
1) フードシステムにおけるガストロノミーとは?
ガストロノミーは単なる「美食」の意味にとどまらず、食材の背景、調理法、食文化、地域性、持続可能性などを総合的にとらえる学際的な概念です。食にまつわる「知」と「技」の総体として、以下のような広がりを持ちます:
- 食材の生産方法や 土地性
- 伝統的・革新的な調理技術
- 地域文化や風土、物語性
- 観光との結びつき(=ガストロノミーツーリズム)
- 食と環境・健康・倫理の関係性
2) フードシステム+ガストロノミーの統合が生む価値
ガストロノミーの視点をフードシステムに組み込むと、以下のような価値が創出されます。
- 地域の一次産品に「意味と物語」が付加される
たとえば、「地元の有機野菜」や「昔ながらの手法で仕込んだ味噌」が、高級レストランのコース料理や地元のガストロノミー体験の素材になることで、食材のストーリーや生産者の哲学が可視化されます。
- 食のクラスターにクリエイティブ産業が加わる
料理人、デザイナー、ツーリズム事業者、メディア関係者などが関与することで、異業種連携による新たな地域ブランドが形成されます。
- 食文化を軸にした地域アイデンティティが強化される
「食べに行くべき町」として観光客や移住者を引き寄せる磁力が生まれます。例:北海道・ニセコ、長野・軽井沢、京都・美山など。
【事例】山形県・鶴岡市:ガストロノミー×在来作物×ユネスコ創造都市
鶴岡市は「ユネスコ食文化創造都市」に認定されており、地域の在来作物を活用した六次産業化と食文化ツーリズムを展開しています。
- 伝統野菜を軸にした加工食品(味噌・漬物・料理)
- 地元シェフとの連携によるガストロノミー体験
- 食育や農業体験のプログラム化
- 農家・料理人・観光業者の連携クラスター形成
➤ 地元の「食の知恵」と「現代の表現」が融合した、新しい地域ブランドの創出事例。
3) ガストロノミーはフードシステムの価値を深化させる
ガストロノミーを取り入れることで、フードシステムは「物を売る仕組み」から、「文化や物語を体験する仕組み」へと進化します。六次産業化のプロジェクトや地域振興政策において、ガストロノミー的視点を導入することは、地域の食を世界に発信し、経済・文化・観光を統合する強力なエンジンとなるでしょう。
3.観光開発と地域ブランド:食を軸にした地域の再構築
1)食の観光資源化
フードシステムを軸にした地域づくりは、観光振興やブランド形成とも強く結びついています。フードシステムの高度化は、観光と深く結びつきます。農業体験や地元の料理を楽しむ「食の観光資源化」は、地域ブランドの形成と相互に連動し、“この土地ならではの体験”としての価値を創出します。
- 「食べるために訪れる地域」への転換
- 農業・漁業体験と連動した教育的ツーリズム
- 「地域らしさ」を前面に出したパッケージ商品の展開
- SNSやふるさと納税でのブランド発信
2)食を軸にした観光開発とは何か?
「食」による観光開発とは、単に地元の食材を提供することにとどまらず、地域の生産や食文化に触れる体験を通じて、価値ある観光を創出する取り組みです。具体的には、以下のようなタイプがあります。
- 農業・漁業体験
収穫体験や漁業体験、放牧など、生産の現場に触れる体験型観光 - 食文化体験
郷土料理づくりや発酵食品の仕込み、農家レストランでの食事など、地域の食文化を学び味わう体験 - ガストロノミーツーリズム
地域の風土や歴史、物語に基づいた料理やコース料理を通じて、深い食の体験を提供する観光 - 地産地消型観光(フードツーリズム)
食材がどのように流通し、どこで消費されているのかを体感できる仕組みづくり
これらの観光開発はすべて、フードシステムの川上(生産)から川下(消費)までの各段階に観光要素を組み込むことで成立しています。食を通じて地域を知り、体験する観光スタイルは、地域の魅力を再発見し、経済循環を生む新たな地域戦略となっています。
3)フードシステムの視点で考える地域ブランド
地域ブランドをフードシステムの視点でとらえると、それは単なる特産品や料理の名前ではありません。重要なのは、地域の食に関わる一連の関係性の中で、どれだけ新たな価値を生み出し、物語を発信できるかということです。
ブランドの強化には、以下のような要素が鍵となります。
- 商品の質
川上の生産段階における技術や自然条件の良さが基盤となります。たとえば、有機農法で育てた野菜や、豊かな漁場で獲れる魚など、地域の自然やこだわりの生産方法がブランドの信頼性を支えます。 - ストーリー性
食材や料理に込められた地元の歴史や文化、伝承、風土といった背景が、ブランドに深みと独自性を与えます。消費者が「その土地の物語」を感じられることが重要です。 - 消費者との接点
商品がどのように届けられ、体験されるかも重要です。販売チャネルや観光体験、SNSでの情報発信など、川下の段階でのブランド体験設計が求められます。 - ネットワーク形成
地域ブランドの土台には、農業者、加工業者、観光業者、自治体など多様な関係者の連携があります。こうした連携がクラスターとして機能することで、地域全体としてのブランド力が高まります。
このように、地域ブランドの構築とは、地域フードシステム全体をつなぎ直し、その構造を「見える化」しながら価値化していくプロセスなのです。
【事例】長野県・小布施町:栗を活かしたブランド化と観光振興
長野県小布施町は、地元特産の栗を活かして、農業・観光・文化を一体化させた地域ブランドづくりに成功した代表的な自治体です。この取り組みは、地域内で生産から消費、さらには文化・体験までを結びつけたフードシステム型の地域戦略といえます。
● 地元産栗を軸にしたスイーツと観光施設の整備
小布施町では、栗の栽培から加工・販売に至るまでを地元主導で展開しています。特に、栗を使ったスイーツや和洋菓子、栗ごはんなどは全国的な人気を集めており、栗専門のカフェや菓子店が立ち並ぶ観光エリアが形成されています。これにより、川上(生産)〜川下(販売・観光)をつなぐ価値の連鎖が実現しています。
● 農家と観光業者の協業による体験型観光の創出
地元農家と観光事業者が協力し、農家民宿や観光農園も展開。栗拾いや加工体験など、食のストーリーに「触れる」「体験する」観光スタイルが確立されています。これは、フードシステムにおける「消費者との接点」を地域内に組み込んだ成功例です。
● 栗 × アート(葛飾北斎)によるブランド融合
小布施は江戸時代に葛飾北斎が滞在した町としても知られており、栗とともに文化資源(北斎館)を観光資源として活用しています。栗を味わうために訪れる人が、アートや町並みにも触れられる設計となっており、フードシステムに「文化的体験」を重ね合わせた高度なブランド構築が実現されています。
4)地域の再構築とは?
フードシステムから観光とブランドを再構築する取り組みは、次のような地域変革をもたらします:
- 経済面:地域内バリューチェーンの強化と雇用創出
- 社会面:住民参画型の観光・ブランド形成による誇りと学び
- 文化面:伝統食文化や風土の保存・再発見
- 環境面:地産地消と持続可能な生産による環境配慮型ツーリズム
5)フードシステムは地域の統合プラットフォーム
食の生産から観光・文化・消費者までをつなぐフードシステムの視点から観光開発や地域ブランドを構築することは、地域社会の経済的・文化的・環境的な再構築を促す強力な方法です。地域の未来は、「どんなものを作るか」ではなく、「どんな関係を育てるか」にかかっています。フードシステムはその関係性をつなぐ「統合のプラットフォーム」なのです。
4.食糧産業クラスター:地域の食産業がつながり支え合う仕組み
フードシステムを地域に根づかせ、持続可能にするには、空間的・産業的な連携構造=食糧産業クラスターの形成が不可欠です。
- 川上(生産)―川中(加工)―川下(販売・消費)を結ぶ
- 企業・農家・飲食店・観光業者・大学・自治体が連携
- 地域全体で食のバリューチェーンと知的生産ネットワークを形成
このように、食を基軸とするクラスター形成が、フードシステム全体を強靱にし、地域を持続的に支えるのです。
1)食糧産業クラスターとは?
食糧産業クラスターとは、フードシステムの各段階に関わる事業者や組織が、地域内で地理的に集積し、互いに連携・補完・協業する仕組みを指します。
特徴:
- 産業の多段階的連携:生産(川上)から加工・流通(川中)、販売・観光(川下)までを網羅
- 異業種・異主体の協働:農家、加工業者、観光業者、大学、自治体、NPO、金融機関など
- 地理的近接性と人的ネットワーク:物理的距離の近さによる知識・技術・人材の交換
- 地域経済の自立的循環:外部依存を減らし、地域内での付加価値創出と再投資を促進
2)フードシステムの視点から見る産業クラスターの意義
フードシステムの視点で産業クラスターを捉えると、食糧産業クラスターは地域の食に関わる多様な活動を結びつけ、持続可能な仕組みとして機能することが分かります。以下に、各領域における意義を整理します。
- 生産の領域:地域の自然資源や知見を共有し、協同農業の展開やスマート農業の導入といった、新たな農業の形をつくることが可能になります。
- 加工の段階:小規模な加工施設を地域で共同利用したり、商品開発において事業者同士が連携することで、多様な商品展開が生まれます。
- 流通・販売:地産地消のルートを確立し、物流の効率化や地域全体でのマーケティング活動の共有が可能となります。
- 観光・外食分野:地域の食文化を活かしたガストロノミー体験や、直売所、食に関するイベントの共同企画を通じて、交流と消費の場が広がります。
- 知識・教育面:地元の大学や研究機関と連携しながら、研究開発(R&D)や食育、農業教育などの知的基盤が強化されます。
- マネジメント面:地域ブランドの統合的な管理や人材育成、さらには政策への提言など、地域全体を見渡した戦略的運営が可能となります。
このように食糧産業クラスターは、フードシステムを地域単位で持続可能にマネジメントするための重要な枠組みであると言えるでしょう。
【事例】北海道・十勝:広域連携による「食と農」の一大フードバレー
北海道十勝地域は、日本有数の農業地帯として知られていますが、現在は「フードバレーとかち」というビジョンのもと、生産から加工・研究・販売・人材育成までを網羅した広域的な六次産業化が進められています。
- 広大な畑作地帯での原材料生産(小麦・豆・野菜・乳製品)
- 十勝産のチーズ、菓子、冷凍食品などの加工品開発
- 地域食品企業と大学・研究機関との連携
- 観光やレストランとの連動による食の体験型プログラム
このように、官民学の連携を基盤にしたクラスター形成が進み、「地域全体を一つの食産業都市」として構想する取り組みが進行中です。
3)フードシステム × クラスターの相乗効果
フードシステムの各要素を地域内でクラスターとして組織・連携することで、以下のような相乗効果が期待されます:
- 川上~川下の連携強化
→ 生産から加工、流通、販売までのバリューチェーンを密接につなげ、高付加価値化を実現 - 経済の地域内循環
→ 地元企業や事業者の活性化により、地域内での雇用創出と所得の再投資が促進される - 持続可能性の向上
→ 生産・加工の過程で資源を効率的に活用し、フードロスの削減にも貢献 - 消費者との関係性の構築
→ 地元ブランドの信頼性向上や、観光・物産を通じた消費者接点の強化が可能に - 多様な主体の協働
→ 農業者、食品事業者、観光業者、自治体、NPO、大学などが連携し、革新と包摂的な地域経済の両立が進む
4)クラスターはフードシステムの地域基盤
食糧産業クラスターの形成は、フードシステムを空間的・制度的に実装するための戦略的手段です。それは、単なる集積ではなく、地域全体で食の価値を共創し、未来へつなげる仕組みとも言えます。『フードシステムの「つながり」を、クラスターが「地域の力」へと変えていく。』それが、食を通じた持続可能な地域社会の鍵となります。
5.結論:フードシステムを核にした地域づくりへ
フードシステムに、六次産業化・ガストロノミー・観光開発・地域ブランド・クラスター形成という複層的な要素を統合することで、地域は「食べる」以上の価値を生み出す拠点になります。それは、地域の産業構造を再編し、文化や風土を表現し、交流と学びを生み、持続可能性を支える総合的な地域戦略でもあります。食は、地域の「未来」を耕すキーワードです。
<参考文献>
時子山ひろみ、荏開津典生、中嶋康博(2019)『フードシステムの経済学』医歯薬出版
斎藤修(2007)『食料産業クラスターと地域ブランド』農文協
【高知県・馬路村】全国町村会:高知県馬路村/地域資源を生かした村の活性化~村をまるごと売り込む~