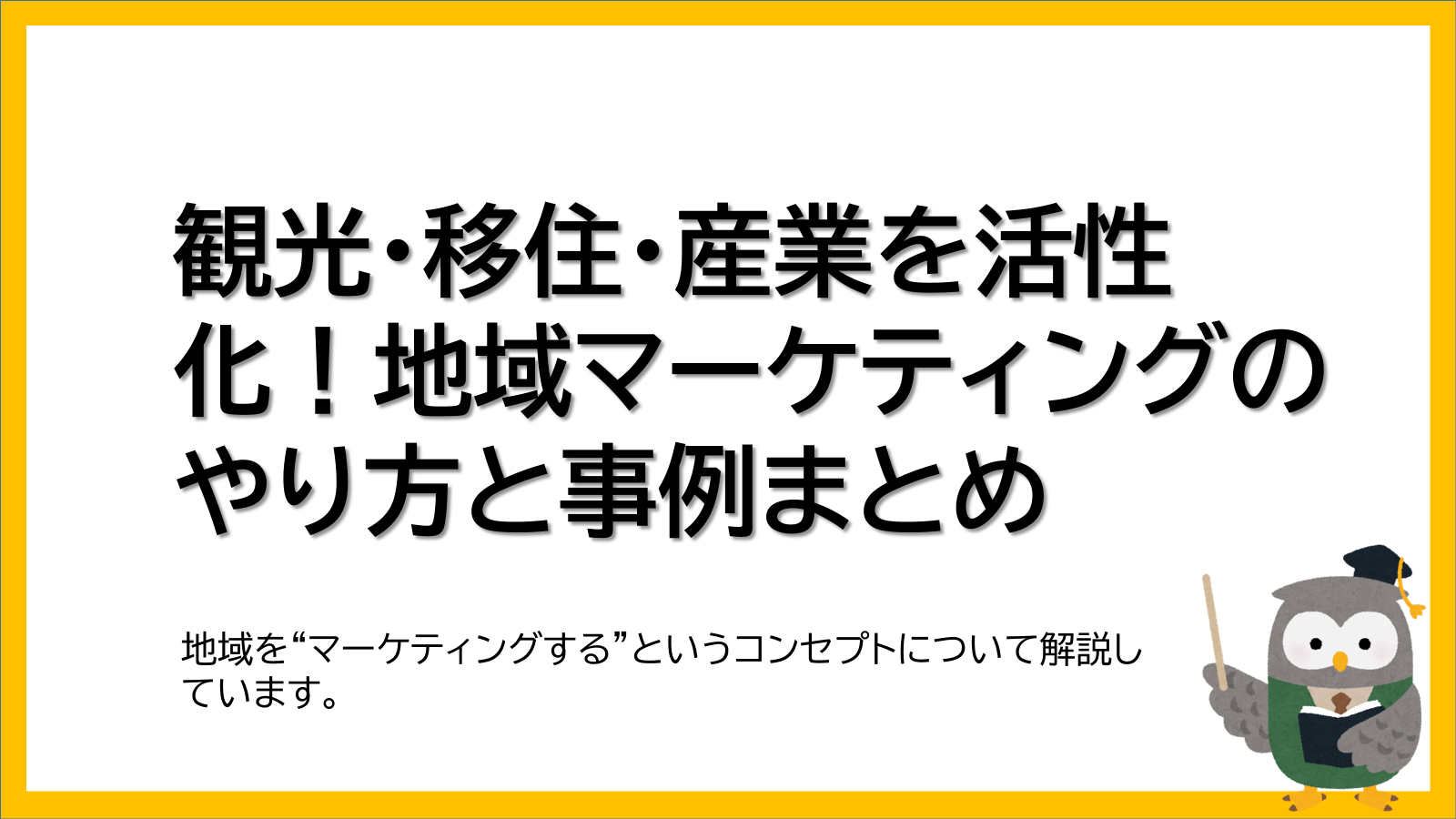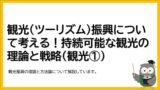地域の魅力をどう伝え、活性化につなげるか——そのヒントが「地域マーケティング」にあります。地域資源の発掘、ブランドづくり、観光・移住戦略、デジタル活用まで、実例を交えてわかりやすく解説します。
<関連記事>
1.地域をもっと元気に!地域マーケティング入門:魅力を発見し、伝える仕組みづくり
「このまちにもっと人が来てほしい」「若者が残り、活躍できる地域をつくりたい」——そんな願いを持つ人にとって、今注目されているのが「地域マーケティング」という考え方です。
これは、企業が使ってきたマーケティングの手法を地域に応用し、「選ばれる地域」を戦略的につくっていこうというアプローチです。観光、移住、地場産業の活性化、関係人口づくりなど、地域を元気にするあらゆる取り組みの基盤として、今や欠かせない視点となっています。
2.なぜ今、地域マーケティングが必要なのか?
少子高齢化、人口減少、東京一極集中——これらの課題は、地方の経済や社会の持続性に大きな影を落としています。地域では、商店街の空洞化、産業の衰退、公共サービスの縮小などが進行しています。こうした中、国も「地方創生」の旗のもと、ふるさと納税や関係人口施策、観光支援など様々な政策を展開していますが、肝心なのは「地域が自らの価値に気づき、それをどのように届けていくか」です。
地域マーケティングとは、簡単に言うと、「地域のファンを増やし、地域を元気にするための戦略的な活動」のこと。
地域が持っている宝物(自然、文化、歴史、人、特産品など)を最大限に活かして、
- 誰に(ターゲット)
- 何を(地域の価値)
- どうやって伝えるか(戦略・手法)
これをしっかり考えて実行するのが地域マーケティングです。目的は、観光客や移住者を増やすだけでなく、地域に住む人たちの「地元愛(シビックプライド)」を高め、持続可能な地域をつくること。企業のように利益だけを追求するのではなく、「公共的な価値」と「住民との共創」が大切になるのが特徴です。
3.地域資源の発見と再評価:価値は足元にある
マーケティングは「資源の発掘」から始まります。地域には、自然、文化、歴史、食、産業、そして人といった多様な魅力が眠っています。しかしそれらは、あまりに日常的であるがゆえに、地域の中の人が見落としがちです。
- どんな資源がある?:山や海などの「自然」、お祭りや古い町並みなどの「文化」、特産品や地場産業などの「産業」。目に見えるものだけでなく、人の知識や経験、地域の歴史といった「目に見えないもの」も大切な資源です。
- 強みと弱みは?:「SWOT分析」(強み・弱み・機会・脅威を分析する手法)などを使って、客観的に地域を見つめ直します。観光資源は豊富だけどアクセスが不便…など、現状を把握することが大切。データ(人口、観光客数など)も参考にしましょう。
- 他との違いは?:他の地域と比べて、どんなユニークな魅力があるのか?(差別化)。真似するのではなく、自分たちらしさを磨くことが重要です。
【事例】宮崎県日南市の油津商店街では、かつて5割以上が空き店舗という深刻な状況にありました。けれど市と住民はあきらめず、外部のIT企業を誘致し、働く場所と地域の日常をつなぐ「サテライトオフィスのある商店街」へと再生。人の流れが戻り、地域への関心も高まりました。
このように、「古くなったもの」「役目を終えたもの」に見える資源でも、視点を変えれば大きな可能性を秘めているのです。
4.ブランドづくりは「共感」から始まる
発掘した資源を、どうすれば“魅力あるかたち”で伝えられるのでしょうか?ここで必要になるのが「地域ブランド」の視点です。
見つけた「価値」を、分かりやすく伝えるための「顔」=地域ブランドを作りましょう。
- ブランドって?:ロゴやキャッチコピーだけではありません。「〇〇といえば、あの地域!」と思い浮かべてもらえるような、地域全体のイメージやストーリーのことです。
- なぜ大切?:認知度が上がり、人が集まりやすくなるだけでなく、住民の誇りや一体感も生まれます。特産品が売れたり、ふるさと納税が増えたりする経済効果も!
- どうやって作る?:地域の核となるコンセプトを決め、共感を呼ぶストーリーを作り、SNSやウェブサイト、イベントなどで一貫して発信していきます。作って終わりではなく、育てていく意識が大切です。
【事例】長野県小布施町は、栗と葛飾北斎のアートを組み合わせたブランディングで全国に知られる町となりました。美しい町並みとアート施設、洗練されたショップが統一感ある世界観をつくり上げ、訪れる人の心をつかんでいます。
<リンク>小布施ブランド戦略の概要
5.誰に届ける?ターゲットを明確に
すべての人にウケる地域など存在しません。だからこそ、「誰に、何を届けたいのか」を明確にするターゲティングが重要です。
- なぜ絞るの?:すべての人に響くメッセージはありません。ターゲットを明確にすることで、より効果的なアプローチができます。
- どうやって絞る?:年齢層(若者、子育て世代、シニアなど)やライフスタイル(アウトドア派、文化好きなど)で市場を分け(セグメンテーション)、特に届けたい人物像(ペルソナ)を具体的に設定します。「東京在住で地域活性に関心のある21歳の大学生、〇〇さん」のように。
- 立ち位置を決める(ポジショニング):競合地域と比べて、自分たちの地域がターゲットにとってどんな価値を提供できるのか、立ち位置を明確にします。
【事例】福井県鯖江市は「めがねのまち」として知られていますが、近年は若い女性やクリエイター層に向けて、“おしゃれで知的な眼鏡”というブランドを打ち出しました。地場産業にデザインや体験を掛け合わせた結果、新しいファン層を獲得することに成功したのです。
<リンク>福井 鯖江 めがね総合案内サイト
地域には多様な関係者が存在します。観光客、移住者、地域住民、企業——それぞれのニーズに応じた施策が必要です。
6.SNS・イベント・商品開発…多角的に伝える
地域の魅力を伝えるには、戦略的なプロモーションも欠かせません。SNSの活用、現地イベントの開催、商品パッケージの工夫、都市部での発信…。そのすべてが「ファンをつくる」ための仕掛けになります。
- 魅力的な商品開発:地域の資源やストーリーを活かした「ならでは」の商品を企画。ターゲットに合わせてデザインやパッケージも工夫します。(例:伝統工芸品を現代風にアレンジ)
- どうやって届ける?(販路):オンライン(ECサイト、ふるさと納税)とオフライン(直売所、道の駅、都市部のイベント出展)を組み合わせます。
- どうやって知ってもらう?(プロモーション):
- オンライン:SNS(特にInstagramなど)での発信、Webサイトでのストーリー紹介が有効。
- オフライン:地域のイベントでの体験ブース、地元メディアとの連携なども大切。
- オンラインとオフラインを組み合わせた「プロモーションミックス」で、多角的にアプローチします。
【事例】山形県鶴岡市の庄内柿では、柿を若者向けに再パッケージし、SNSで発信することで都市部で話題に。「昔ながらの特産品」を“かっこよく再編集”したこの取り組みは、地元の農業への誇りを再発見させるきっかけにもなりました。
<リンク>食の都 庄内 庄内柿
7.デジタル時代の地域づくりへ
地域マーケティングは、もっと面白く、もっと深く進化していきます!
- DX(デジタル)との融合:AIによる需要予測、メタバースでの仮想観光、データ分析による効果的な施策など、テクノロジーが地域課題解決や新たな価値創造を後押しします。
【事例】香川県高松市「スマートシティたかまつ」:AIやIoTを活用し、交通、福祉、防災など多分野で市民・企業・行政が連携して課題解決に取り組んでいます。
- 「関係人口」を増やす:移住・定住だけでなく、地域と継続的に関わる「ファン」を増やすことが重要に。オンラインイベントやクラウドファンディングなど、多様な関わり方をデザインします。
- SDGsとの連携:環境保全、地域内経済循環、多様性の尊重など、持続可能な社会を目指すSDGsの視点は、これからの地域マーケティングに不可欠です。地域の取り組みが、社会全体の目標達成にも貢献します。
<リンク>スマートシティたかまつ
8.未来の地域マーケターへ:あなたの一歩が地域を変える
これまで紹介してきたように、地域マーケティングとは、地域の魅力を発見し、戦略的に届けるための「まちづくりの考え方」です。そして、その主役は行政や企業だけではなく、住民、学生、外部人材など、あらゆる人々です。
皆さんには、ぜひ地域に出かけ、話を聞き、企画を考え、発信してみてほしいと思います。特別な知識や技術がなくても大丈夫。地域を知り、関わり、想いをもって行動することで、誰もが地域を元気にする担い手=地域マーケターになれるのです。
あなたの一歩が、地域の未来を変えるかもしれません。